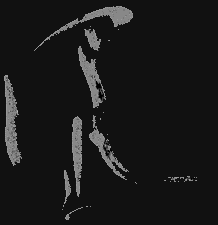top of page
© Copyright
木 村 尚 樹
fine photographic arts
Artist Statement
世界は、光と空気、そして静けさのゆらぎの中で、そっと姿をあらわす。
私が撮るのは、対象を記録するためでも、感情を語るためでもない。
世界がひらき始めるその瞬間に、ただ立ち会っている。
情緒は、内面を表すものではなく、
世界の微かな震えを察知する 知覚の閾(いき) として働いている。
写真に写るのは「見たもの」ではなく、知覚と世界がかすかに重なった、
一度かぎりの現れの痕跡である。
モノクロームは、世界を簡略化するのではなく、
現れが立ち上がる余白をつくる。
その静かな余白の中で、美はつくられるのではなく、そっと生じる。
私はその閾を 零の地平(Zero-Horizon) と呼ぶ。
表象がほどけ、ただ「ある」という気配だけが残る場所。
撮るとは、奪うことではない。
受けとめることである。
私は、その現れの中に、静かに佇んでいる。
木 村 尚 樹
木 村 尚 樹
fine art photography
bottom of page